MD-Blog_Web Creative
AIが進化しても、デザイナーにしかできないこと
 ここ一年でAIはデザインの現場に急速に浸透し、話題になっていますよね。
ここ一年でAIはデザインの現場に急速に浸透し、話題になっていますよね。
最近は、このMDブログもAIの記事でいっぱいになっていますw
もちろんWebデザイン界隈もAIの話題でいっぱいです。
FigmaにAI機能が搭載され、ChatGPTやなんやらでサイト案が一瞬で生成できる時代で、
「AIがあれば、もうデザイナーはいらないのでは?」という声すら聞かれるようになりましたが...。
しかし、実際のデザイン現場で働いていると、AIは確かに「速い」けれど、まだまだ全てを任せられるわけではないと感じませんか?
本ブログでは、デザイナー(私)がAIを制作現場に導入して、人間(デザイナー)にしかできないと感じた仕事についてまとめたいと思います。
意図をデザインする
デザイナーは、クライアントから「もっとスタイリッシュに」「明るい感じで」と言われたとき、
その言葉に含まれる「意図」を探り、表現することがデザイナーの仕事だと考えています。
たとえば「スタイリッシュにしたい」の背景には、「信頼感を出したい」「採用を強化したい」「若い層に響かせたい」など、さまざまな意図が隠れています。
AIは与えられた指示どおりに見た目を整えることはできますが、その言葉の裏にある文脈や感情を読み取ることはできません。
デザイナーは、相手の表情や声のトーンから意図を感じ取り、「本当に必要なデザイン」へと導くことができます。
体験設計(UX)
ユーザー体験(UX)を考えるとき、デザイナーは「どうすれば迷わずに目的を達成できるか」だけでなく、
「どんな気持ちでこのサイトを使っているか」まで想像します。
たとえば、病院のサイトを訪れるユーザーは不安を抱えています。
その気持ちを和らげるために、色味や言葉、写真の雰囲気を慎重に選ぶ。
これが世界観であり、共感から生まれるデザインかと思います。
AIは過去のデータから「多くの人が好む構成」を提案できます。
しかし、「この人はきっと今、少し緊張してるかもしれない」という感情まではわかりませんので、
デザイナーがUXを「体験」として成立させるには、リアルな感情を理解し、そこを表現する視点が欠かせません。
翻訳して表現する力
デザインには、その土地や文化が反映されていきます。
たとえば、「間」や「余白」などは単なるレイアウトの空白ではなく、世界観の演出でもあります。
AIに「和風で上品なデザイン」と指示しても、生成されるのは海外の「Japanese風」なもので、
余白などを考慮した、本当の日本的なデザインまでは表現が難しいと感じています。
デザイナーは、文化・時代・価値観を理解し、ブランドが持つ世界観を「翻訳」してデザインに落とし込みます。

対話から生まれるデザイン
良いデザインは、ひとりのデザイナーから生まれるものではなく、
クライアント、エンジニア、マーケター、コピーライターなど、さまざまな人が関わり、意見を交わしながら形になります。
その中でデザイナーは、ビジュアルを整えるだけでなく、会話をまとめて、形にする存在だと思います。
曖昧なアイデアを整理し、関係者の考えを引き出し、みんなが同じ方向を向かせるのことはAIにはできません。
AIはあくまでツールなので、
人と人をつなぎ、チーム全体を動かすのは、デザイナーとしてのコミュニケーション力ですよね。
AIを味方に
ここまで「AIにできないこと」を語ってきましたが、
もちろん、AIはまだこれができないなどと排除する必要はまったくありませんし、
むしろ、AIを活用できるデザイナーこそが強い時代になってきたかと思います。
AIは、アイデアの初期案づくりやパターン出し、資料作成など、
「時間のかかる部分」を圧倒的に効率化してくれますので、
デザイナーはより多くの時間をデザイン作業に使えるようになります。
今後もAIがもっと進化し、デザインを作れるようになったとしても、
深くユーザーを考えたデザインを作れるのは、まだ人間だけではないでしょうか?
それは、私たちがユーザーの気持ちを理解し、ユーザーのために作るという意識を持っているから。
AIの進化が加速する今こそ、人間(デザイナー)にしかできない体験をデザインに落とし込むことが、
最高のスキルになるのかもしれませんね。
...そう今はね。
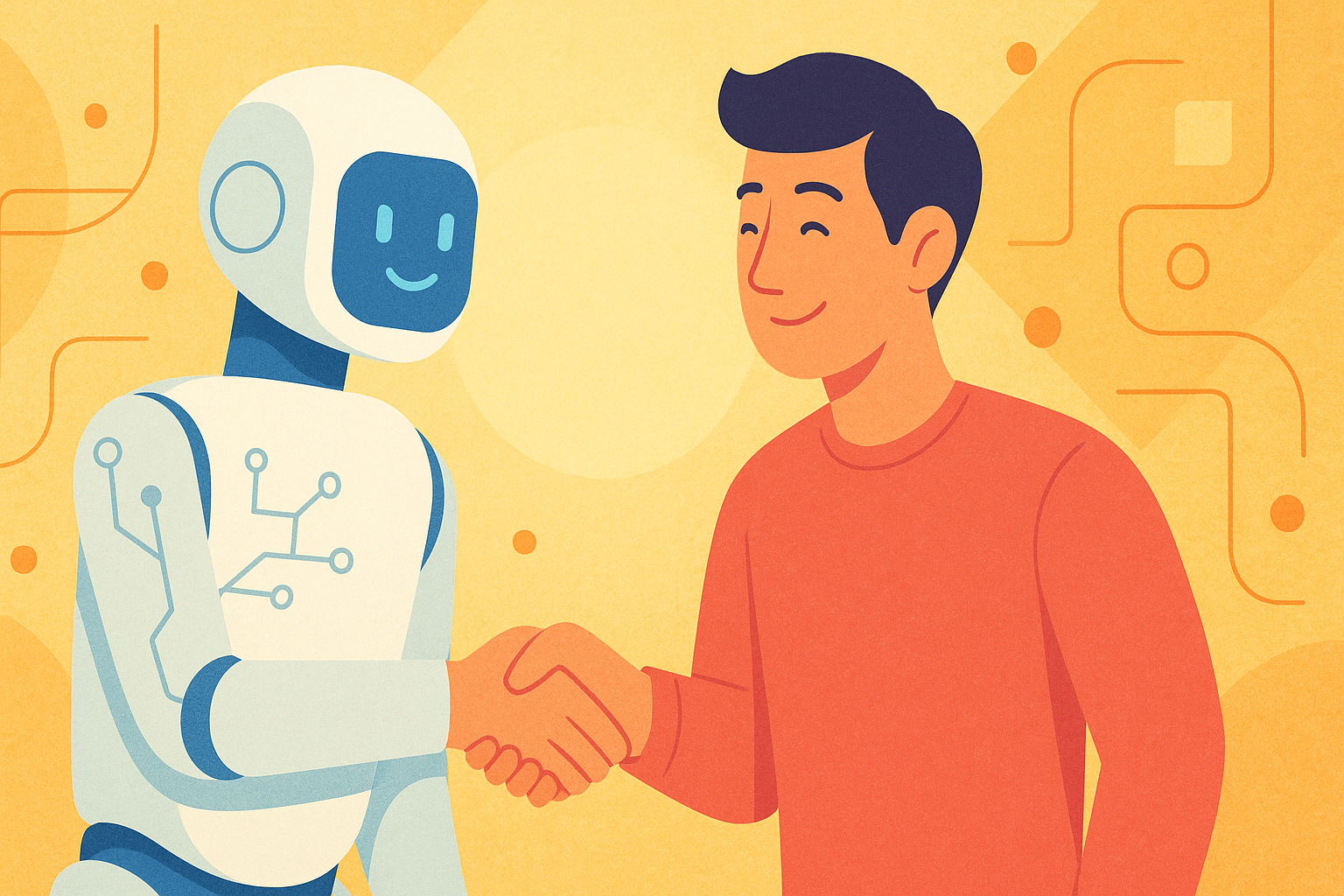
- Recent Entries
-
- やりたい事やったら、みんなが仲良くなった話
- 配信現場ディレクターの1日。 配信の裏側でどのような準備が行われているのか。
- WordPress×Bogoでスムーズな切り替えを実現する 自由度の高い多言語サイト制作
- 誰でも簡単にクイズイベントが開催できる! Webサービス『Quizzy』(クイジー)の魅力を紹介
- 配信・収録・バーチャルプロダクションまで。 「MONSTERSTUDIO乃木坂」の活用方法を紹介
- チームリーダーとして、バラバラな強みをひとつのチームにするということ
- 【18年目の挑戦】MONSTER DIVE 2026 KICK-OFF!
- 「課題を解く力」で世の中を動かす--WEBプロダクション事業部2026年の決意
- 2025年17期を振り返って。さらなる高みを目指す18期への決意
- Webデザイナー、急にYouTuberデビュー
- MD EVENT REPORT
-
- よりよいモノづくりは、よい仲間づくりから 「チームアクティビティ支援制度」2025年活動報告!
- MDの新年はここから。毎年恒例の新年のご祈祷と集合写真
- 2024年もMONSTER DIVE社内勉強会を大公開!
- 社員旅行の計画は「コンセプト」と「事前準備」が重要! 幹事さん必見! MONSTER DIVEの社内イベント事例
- 5年ぶりの開催! MONSTER DIVE社員旅行2024 "Build Our Team"!
- よいモノづくりは、よい仲間づくりから 「チームアクティビティ支援制度」2023年活動報告!
- 2023年のMONSTER DIVE勉強会を大公開!
- リフレッシュ休暇の過ごし方
- 勤続10周年リフレッシュ25連休で、思考をコンマリしたりタイに行った話。
- 俺たちのフジロック2022(初心者だらけの富士山登山)
- What's Hot?
-
- 柔軟に対応できるフロントエンド開発環境を構築する 2022
- 楽しくチームビルディング! 職場でおすすめのボードゲームを厳選紹介
- ライブ配信の現場で大活躍! 「プロンプター」とは?
- 名作ゲームに学べ! 伝わるUI/UXデザインのススメ
- 映像/動画ビギナーに捧げる。画面サイズの基本と名称。
- [2020最新版] Retinaでもボケない、綺麗なfaviconの作り方
- ビット(bit), バイト(Byte), パケット。ついでにbps。 〜後編「で、ビットとバイトって何が違うの?」〜
- 有名企業やブランドロゴに使われているフォントについて調べてみる。
- 算数ドリル ... 2点間の距離と角度
- 画面フロー/システムフローを考えよう!
- タグリスト
-
- #Webデザイン
- #JavaScript
- #MONSTER DIVE
- #ライブ配信
- #映像制作
- #Movable Type
- #CMS
- #ワークスタイル
- #MONSTER STUDIO
- #Webプロモーション
- #Web開発
- #Webディレクターのノウハウ
- #アプリ
- #Creators Lab まとめ
- #MTタグを極める
- #MD社内イベント
- #効率化
- #Webクリエイティブ
- #CSS
- #撮影
- #Webディレクション
- #プランニング
- #コーディング
- #ストリーミング配信
- #オーサリング
- #クレバー藤原
- #スマートフォン
- #早朝がいちばん捗るヒト
- #PowerCMS
- #WEBサービス
- #ライブ中継
- #グラフィックデザイン
- #人事
- #サマンサ先生
- #AI
- #Android
- #Webメディア
- #まとめ
- #ディレクション
- #HTML5
- #iPhone
- #プラグイン
- #プログラミング
- #新入社員
- #iOS
- #jquery
- #RIDE HI
- #UI/UXデザイン
- #アニメーション
- #Adobe
